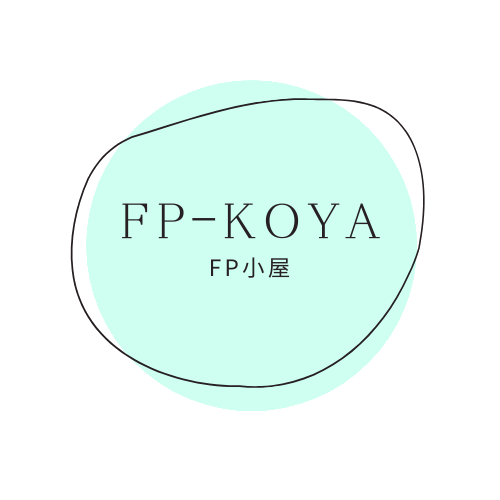(最終更新月:2022年11月)
✔当記事はこのような方に向けて書かれています。
「持病があっても保険に入れるのか知りたい」
「どんな病気だと入れないんだろう?」
「入れる保険があるとしたらどうやって選べば良いの?」
✔当記事を通じてお伝えすること
- 保険に入りづらい持病や病気について
- 保険は条件付きで入れる場合もある
- 持病持ちでも入れる引受緩和型の保険について
当記事では、保険に入りづらいといわれている持病や病気についてはもちろん、保険に入れる場合があることや入れる可能性の高い引受緩和型の生命保険についてご説明しています。
ぜひ最後までご覧ください。
保険に入りにくい持病とは?

持病とは、「慢性疾患」や「基礎疾患」と呼ばれるなかなか治らない病気のことです
持病といわれる主な病気は、以下の通りです。
- 高血圧
- 腎臓病
- 肝臓病
- 心臓病
- 糖尿病
- 喘息
- 神経症
- 痛風
- 腰痛
保険は条件付きで入れることもある

持病があっても、特別な条件付きで保険に加入できる場合があります。
どのような条件があるのか分かれば、自分に合った保険を選びやすくなるのです。
- 保険に入れないことを謝絶という
- 条件付きで保険に入れる3パターン
- 条件が付いたらやるべきこと
保険に入れないことを謝絶という
謝絶とは、健康状態などにより、保険に入れないと判断されてしまうこと。
一般的に保険が入れなかったといわれるのは、謝絶であることを意味します。
保険に加入する方の健康状態や職業により、謝絶される可能性が高くなります。
条件付きで保険に入れる3パターン
条件付きで保険に入れる3パターンをご紹介します。
保険の加入は、◯×の2択ではなく、△で保険に入れることもあるからです。
- 特定の部位や疾病での不担保
- 特別保険料・割増保険料の支払い
- 保険金の削減
特定の部位や疾病での不担保
ひとつ目は、特定の疾病や部位については保障しないという条件です。
発症する可能性の高い病気や身体の部位を対象外にすることで、保険金の支払いリスクを健康な人と揃えます。
例えば胃潰瘍を患ったことのある人は、胃や十二指腸に関して保障されない場合があります。
特定の病気や部位を不担保にすることで、持病のない人との不公平さを軽減しているのです。
特別保険料・割増保険料の支払い
条件付きで入れるケースでよく見るのは、特別保険料や割増保険料の支払いです。
保障の内容は通常の契約と変わりはありませんが、保険料を上乗せすることで持病がない人との不公平さを減らします。
この上乗せされる保険料のことを「特別保険料」や「割増保険料」といい、契約中ずっと上乗せされる場合と契約から一定期間だけの場合があります。
保険金の削減
保険金(保障額)の削減も、条件付き加入であり得ることです。
リスクと保険料に見合う、保障額に調整することで、健康な人との不公平さをなくします。
病気や死亡があった場合、保険会社が決めた期間中は保険金が削減されるというもの。
最長5年間とし、リスクに応じて保険会社が期間を決定します。
条件が付いたらやるべきこと
こちらでは、条件が付いたときにやるべきことを解説します。
するべきことを知っておくと、後々のトラブルを防げ、もっと条件の良い他の保険を検討することもできます。
- 条件の内容を確認する
- 他社の加入要件をチェックする
- ほかの保険種類を検討する
条件の内容を確認する
まずは、条件の内容をチェックしましょう。
その条件で保険に加入するメリットがあるのか確認するためです。
条件付きですから、通常の契約よりも保険料が高くなっていたり、保証が制限されていたりします。
自分にとってデメリットの方が大きくないかなど内容をしっかりチェックしましょう。
他社の加入要件をチェックする
特別条件を確認した結果、「保険料が高すぎる」「希望する保障がない」といった場合には、他の保険会社で似たような保険を探しましょう。
会社によって、告知に対する契約判断が異なるからです。
例えば、A社では条件付きと言われたのに、B社では通常通りの契約ができることもあります。
条件に満足できない場合は、他社の保険を見てみることをおすすめします。
ほかの保険種類を検討する
条件に満足できない場合は、ほか保険を検討するのも一つです。
なぜなら、保険の種類により加入要件が異なる場合があるから。
例えば、医療保険というくくりでも以下のように種類があります。
- 医療保険
- 特定疾病保険
- がん保険
- 引受緩和型医療保険
保険により、告知する項目が少なかったり、告知する必要がなかったりします。
さまざまな種類の保険を比べてみることで、自分の希望に近い保険を見つけられるでしょう。
保険に入れない病気一覧
以下は、保険に加入できない可能性が高い病気一覧です。
どの病気が当てはまるのか知っておけば、自分が保険に入れるかどうかの目安になります。
- がん
- 脳卒中
- 心筋梗塞
- 心不全
- 肝硬変
- 不整脈
- ⼤動脈解離
- 慢性腎炎
- 動脈硬化症
- 糖尿病
- 認知症
- アルコール依存症
- うつ病
- パーキンソン病
保険会社によって加入条件は異なるため絶対ではありませんが、以上の病歴があると保険に加入できない可能性が高くなります。
持病持ちでも入れる引受緩和型保険

持病があっても入りやすい引受基準緩和型についてご紹介します。
加入時の条件が緩和されているので、入れる可能性が高くなるのです。
- 引受緩和型保険とは?
- 引受緩和型保険のメリット
- 引受緩和型保険のデメリット
引受緩和型保険とは?
引受緩和型保険とは、慢性的な持病がある方でも入れるような、加入要件を緩くした保険のこと。
例えば、ある保険会社の引受緩和型保険では、以下のような告知に該当しなければ入れます。
- 過去3ヶ月以内に、医師・歯科医師から、入院、手術、放射線治療(電磁波温熱療法を含みます)をすすめられたことまたは説明を受けたことがありますか。※既に入院をした(退院済)、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含みます)が完了した場合は「いいえ」になります。
- 過去1年以内に、入院をしたこと、または手術、放射線治療(電磁波温熱療法を含みます)をうけたことがありますか。
細かい入院についての定義などはありますが、告知事項が2つだけなので入りやすい保険といえるでしょう。
興味のあるかたはこちらまでご相談ください。
引受緩和型保険のメリット
引受基準緩和型保険のメリットを3つご紹介します。
もしメリットを感じなければ、引受緩和型を検討しなくて良いでしょう。
- 通常の保険で謝絶された人や部位不担保になった人も加入しやすい
- 健康告知の質問項目が少ない
- 持病が悪化したり、再発したりするなど、通常の保険では対象外になる場合でも保障してくれる
保険の告知で嘘を付くことはいけませんが、聞かれていないことにあえて答える必要もないのです。
引受緩和型保険のデメリット
引受緩和型保険のデメリットについて説明します。
引受緩和型の保険もメリットだけではありません。
- 保険料が割高になる
- 定期間は給付金が減らされる
- 選べる保険や特約の種類が少ない
支払削減期間は一般的に、加入から1年以内に支払いが発生した場合は50%削減されるものが多いです。
ただし保険会社によっては、初年度から満額保障の会社も出てきています。
各社の比較を怠らずにおこないましょう。
保険選びの際に見るべきポイント

保険の選び方をご説明します。
さまざまな保険種類があり、どれを選べばいいのか決められない方が多いからです。
- 保険金・給付金
- 保険期間
- 支払保険料
- 支払削減期間
保険金・給付金
まずは、保険金や給付金の金額です。
保険は加入が目的ではなく、万一の際に出る保険金で自分や家族を守るのが目的です。
保険金が足りない場合はもちろん、多すぎることも考えられます。
適切な保険金に無駄なく入れるよう、しっかり確認するのがポイントです。
保険期間
保険期間についても確認しておきましょう。
保険期間には定期型と終身型があり、自分に合った方を選択する必要があります。
- 定期型:家族への責任や一定期間のコストに備えたい
- 終身型:必ずかかる可能性のあるコストに備えたい(葬儀代・相続税など)
保障の目的に合わせて、保険期間を選びましょう。
支払保険料
保険料についても確認しておくべきです。
毎月支払う固定費となるので、高ければ家計の負担になるでしょう。
他社の同類の保険と比べて、割高になっていないかチェックすることをおすすめします。
以下のように保険種類によっても特徴があります。
- 定期型:若い頃は割安ですが、更新するたびに保険料が上がる
- 終身型:保険料は一生変わりませんが、定期型に比べて若いうちは保険料が高い
ライフスタイルに合った負担にならない保険料で加入することがおすすめです。
支払削減期間
引受緩和型の保険では、支払削減期間が設定される場合があります。
加入時に決まっていることなので、どれくらいの期間になるのか把握しておきましょう。
保険会社によっても、期間や削減割合が異なるので、きちんと比較も大切です。
まとめ:保険に入れない病気一覧でも、保険種類を選べば入れることがある
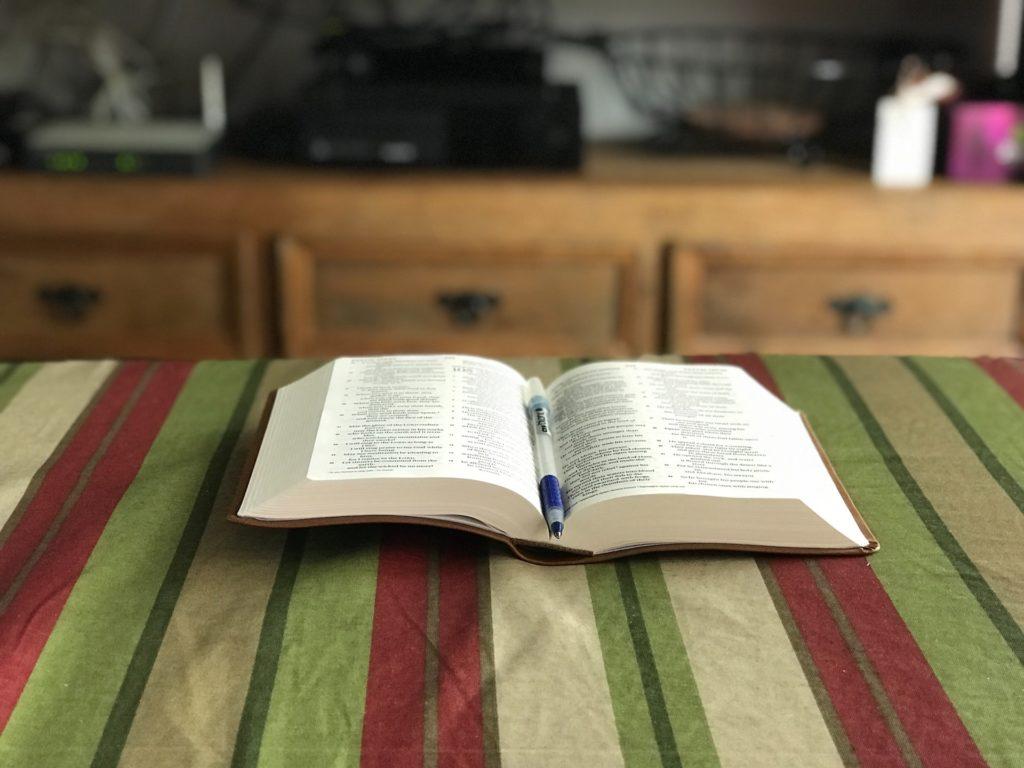
当記事の内容をまとめます。
- 保険の加入は、◯×だけでなく、△もある
- 引受緩和型の保険では、持病があっても入れる
- 引受緩和型の保険に入る時はメリットばかりでなく、デメリットもきちんと把握しよう
保険に入れないといわれている病気をお持ちでも、保険会社により入れる場合があります。
ただしその分デメリットがあるのも事実。
きちんと必要な分だけ無駄なく入れるようにしておくことが大切です。